博多湾上陸
元は支配下に収めた朝鮮半島の高麗に軍船を建造させ、大船団が高麗の合浦(がっぽ)から日本に向かった。1274(文永11)年10月20日(旧暦、以下日付は旧暦)の夜明け前、対馬や壱岐といった日本の防衛線となる島を突破していた約900隻の船団が博多湾に姿を現わした。「文永の役」である。
人馬を乗せた大型の母船、兵士用の小型突撃船(バートル船)、食料・水を積んだ補給船など大小さまざまな船が侵入し、騎馬兵が上陸を試みた。元の指揮下、かなりの高麗人兵士が動員され、実態は「元・高麗連合軍」だ。兵士の数は諸説あり、「数万人」といったところか。
蒙古襲来の研究者として知られる元九州大学大学院教授の服部英雄氏の見立てによると、船団は博多湾沿岸の主に3カ所に向かってきた。中でも元軍が戦力を集中させてきたのは湾の中央部の鳥飼浜だ。

鳥飼浜は今では埋め立てられ、福岡PayPayドームがあるので、もう一つの上陸地点の今津から浜に降りてみた。北の方向に目をやると、山型に膨らみ、漁業が盛んな玄界島が見える。博多湾の入り口よりもやや沖にあるが、陸地からさほど距離がないように感じられる。強い風と速い海流に乗って、元の軍船が湾に差し掛かって上陸するまで、さほど時間を要しなかっただろう。

今津の海岸から博多湾を望む。中央に見えるのが玄界島(筆者撮影)
新兵器を駆使した元軍
鳥飼浜の合戦の模様は、有名な『蒙古襲来絵詞(えことば)』(※1)にも、描かれている。短弓で攻めかかる元軍兵士に対して、肥後国(現在の熊本)の御家人、竹崎季長(すえなが)が馬上から弓を放ち敵に命中させたものの、馬は敵の矢を受け血を流している。さらに元軍の火器「てつはう」がさく裂しているためか、竹崎の馬は驚いてあらぬ方向を向いている。

『蒙古襲来絵詞(模本)』に描かれた鳥飼浜の合戦。右の馬上の武士が竹崎季長、馬のそばで「てつはう」がさく裂している(九州大学付属図書館所蔵)
「てつはう」は、後の「弘安の役」(1281年)の舞台の一つである長崎県・鷹島沖海底で発見され、実在が確認されている。直径13センチほどの陶器製の球体で、火薬が詰め込まれ、導火線で爆発する仕組みだ。『八幡愚童訓』という史料には、「鳴る音が大きいので、(日本兵は)心を迷わし、肝をつぶし、目はくらみ耳は鳴って、ぼうぜんとして方向を失ってしまう」と表現されている。九州大学が撮ったCT画像には、鉄片と陶器片のようなものが映し出されており、殺傷能力もあったとみられる。

「てつはう」(左)、元軍の兜(右)=長崎県松浦市立埋蔵文化財センターで(筆者撮影)
このほか、兵器面で大きく違ったのは弓だ。日本の長弓は遠くへ飛ばすことができるが、馬上での機動性に欠ける。また「右利き用に作られているので右に矢を放てず、敵を左側にする位置取りをしないと射ることができない」と服部氏。これに対して、元軍は機動性のある短弓を使っていた。
新兵器や騎馬の機動力を見せつけて、「緒戦は元軍が幕府軍を押し気味だったのでは」と、服部氏はみる。
警固所
元軍が鳥飼浜に戦力を集中させてきたのは、その近くにある「警固所(けごしょ)」と呼ばれる幕府側の防衛拠点の攻略が狙いだった。警固所は、後の江戸時代に福岡城が築かれた高台にあったとされる。服部氏は「ここを陥落させることができれば、前線基地にできるし、日本の武器も手に入る」とし、元軍は内陸部への侵攻を視野に入れていたとみている。

警固所があったとされる福岡城址の丘。この城は、後の1601年に黒田長政らの手によって築かれた(筆者撮影)
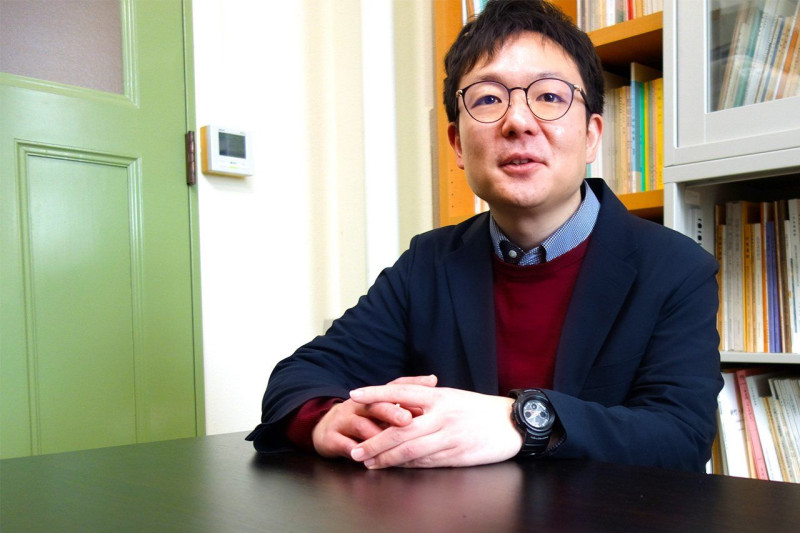
九州大学総合研究博物館の福永将大助教(筆者撮影)
それにしても、日本と交流のなかった元軍は博多湾や警固所をターゲットにすることをどうやって思いついたのだろうか。九州大学総合研究博物館の福永将大助教は「日本に盛んに出入りしていた南宋をはじめとする大陸や朝鮮半島の商人、僧侶が情報源になった可能性がある」と推測する。元に侵攻されていた南宋には、友好国の日本に元の情報をもたらす者もいれば、逆に元に取り入り日本の情報を提供している者もいて、二面性を帯びていたのではないか。
「大宰府合戦」
10月20日、鳥飼浜で日本軍と一戦を交えた元軍は、高台の警固所を攻めきれず、その日の晩は近くの祖原山に陣を構えた。ところが、元軍は翌21日には踵(きびす)を返すかのように姿を消してしまったというのが定説になっている。「神風が吹いて退散した」という説は否定されているものの、元は日本に通交交渉の席に着かせる狙いで、武力で威嚇しに来ただけと言われている。「予定通りの退却」説である。

(左)祖原山に陣取った元軍兵士たち、『蒙古襲来絵詞(模本)』より(九州大学附属図書館所蔵)、(右)現在の祖原山の山頂(筆者撮影)

元九州大学大学院教授の服部英雄氏(服部氏提供)
これに対して、新説を打ち出しているのが服部氏だ。『関東評定伝』という史料の中に、上陸4日後の10月24日に「大宰府合戦」との記述があることに着目。元軍は要衝の大宰府近辺まで南進したとみる。
大宰府には7世紀、日本の防衛・外交の最前線として、政庁が置かれた。大陸と近い九州の地に築かれた朝廷の重要な出先機関だ。海に近い博多では、迎賓館とも言える「鴻臚(こうろ)館」で大陸からの客をもてなす一方、心臓部の政庁は内陸部の大宰府に置き、守りを固めていた。鎌倉時代には、政庁は衰退したが、実質的に幕府の支配下にあった。
その大宰府に元軍は迫って来たというのだ。結末はどうであったのか。この史料には「異賊敗北」と記されており、日本軍が元軍を退けたようである。政庁の防壁とも言える土塁の水城(みずき)(※2)が「高い土手になっており、幕府軍は守りやすかったのではないか」と、服部氏は話す。

上空から見た大宰府政庁跡(時事)

水城跡。建設当時は9メートルもの高さがあったとされる(福岡県太宰府市提供)
元軍は最新の武器を使い、日本側は相当苦戦したとみられるが、「幕府は九州全体の御家人を動員していたため、兵数は元を大きく上回った」。また、10月末という日本海が荒れる季節も相まって、元軍は高麗から物資補給を受けるのが困難だったとしている。
服部説によれば、元軍は1日で退却したのではなく、大宰府政庁に向けて内陸部まで侵入したが、攻めきれず、退却したということになる。「元はこの兵数では勝てないことが分かり、結果として“偵察”になったのではないか」と同氏は言う。
博多湾に「石の防壁」
初めての異国からの侵攻で死傷者を出した幕府は、再侵攻の恐れがあると警戒を強め、防衛強化に乗り出す。元軍が騎馬で上陸してきた衝撃から、「石築地(いしついじ)」と呼ばれる防塁を博多湾沿いにぐるりと張り巡らせた。総延長20キロに及ぶ「石の防壁」だ。

『蒙古襲来絵詞』に登場してくる「生(いき)の松原の防塁」は実際に存在する。博多湾の中西部(現在の福岡市西区)の海岸沿いに200メートル近くの石垣が並ぶ。防塁の裏側に立つと、博多湾が前面に広がる。強い風と波のうねりに乗って、元の軍船が迫って来るかのような錯覚にとらわれる。

「生の松原」防塁の裏側から博多湾を望む(筆者撮影)

『蒙古襲来絵詞(模本)』に描かれた「生の松原の防塁」(九州大学附属図書館所蔵)
石垣の高さは2メートル以上あり、前面は砂浜だ。「元の騎馬隊が上陸しても砂浜で足が取られやすくなるし、高い石垣を乗り越えるのは困難。その間に幕府軍は上から弓で狙い撃ちできる態勢にあった」と、九大の福永助教は話す。
さらに博多湾西部にある「今津防塁」は、「生の松原」に比べて、石垣に厚みがあり、形状が異なる。防塁は鎌倉幕府から号令がかかって、わずか半年以内の急ごしらえだったため、九州各地の御家人が総がかりとなった。生の松原は肥後国が作ったのに対し、今津は大隅国(現在の鹿児島)と日向国(現在の宮崎)が担当し、造りに違いが出た。

今津防塁(筆者撮影)
「文永の役」で馬と共に上陸してきた元軍は、7年後の再侵攻「弘安の役」時には上陸すらして来なかった。湾内に侵入した元の船団からは防塁が張り巡らされているのが目に入ったからではないかと言われている。「石の防壁」は見事に抑止力の役割を果たしたのである。(第3回に続く)
●道案内
- 生の松原防塁:JR筑肥線・下山門駅から北へ徒歩10分
- 今津防塁:JR筑肥線・今宿駅から北へ車で15分
- 福岡城址:地下鉄空港線・大濠公園駅から徒歩3分
- 祖原山:地下鉄空港線・西新駅から南方向へ徒歩15分
- 大宰府政庁跡:西鉄・都府楼(とふろう)前駅から徒歩15分
(※1) ^ 『蒙古襲来絵詞』は元との戦いに参集した肥後国の御家人、竹崎季長(すえなが)が自身の活躍ぶりを絵師に描かせた絵巻。「メモ書き」も添えられている。恩賞欲しさに多少の脚色も含まれているだろうが、同時代性があり、史料価値の高い国宝指定の絵巻だ。
(※2) ^ 日本は663年、百済と共に、新羅・唐と戦った「白村江の戦い」で敗北。報復を恐れて、大宰府政庁防衛のため翌664年に水城と呼ばれる土塁を築いた。高さ9メートル、長さ1.2キロあり、外側には堀を巡らして川から導水した。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。




